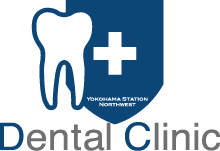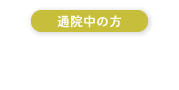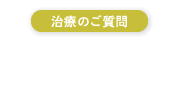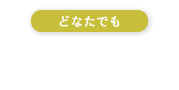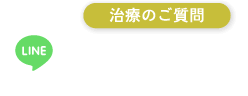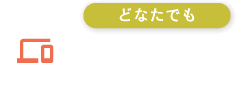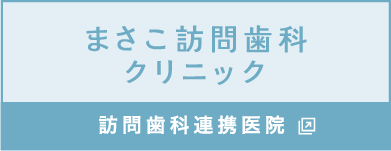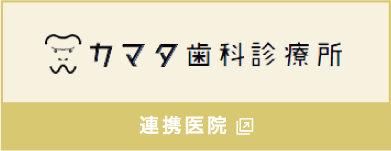こんにちは。横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」です。
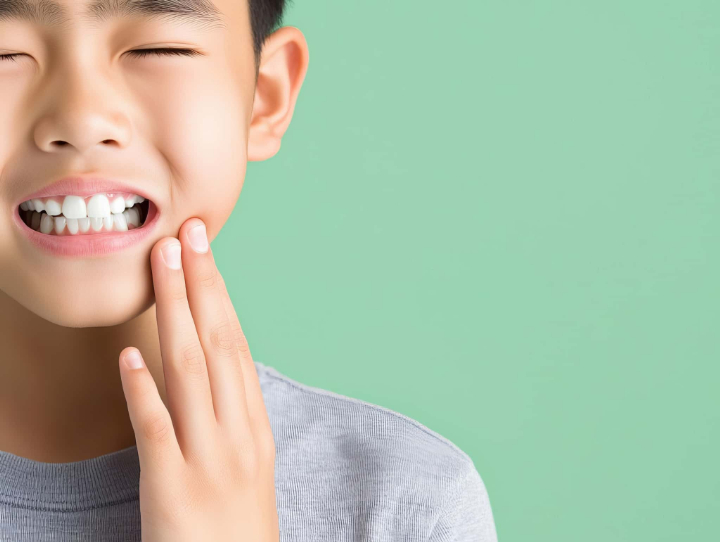
お子さまの歯ぐきが赤く腫れていたり、歯磨きのときに出血したりする場合、歯肉炎かもしれません。歯肉炎を放置すると歯がぐらつき、最悪の場合は歯を失うおそれがあります。
この記事では、子どもの歯肉炎の種類とそれぞれの原因について解説します。歯肉炎を予防するための方法についても紹介しますので、お子さまのお口の健康を守るために、ぜひ参考にしてください。
子どもでも歯肉炎になるの?

子どもでも、歯肉炎になることは珍しくありません。厚生労働省の調査によると、10歳から14歳の子どものうち、約4割が歯肉からの出血があるとされています。
歯肉炎とは、歯ぐきに炎症が起きている状態です。歯ぐきの赤みや腫れ、出血などが生じ、口臭の原因になることもあります。放置すると、歯周組織が破壊される歯周炎へと進行し、歯がぐらついて最悪の場合抜け落ちます。
子どもは、痛みや腫れによる違和感があってもうまく伝えられないことが多く、保護者が気づかないうちに進行しているケースも少なくありません。歯肉炎の段階であれば適切なケアで改善が見込めるため、早めに対処することが大切です。
保護者が仕上げ磨きをして歯周病を予防するとともに、歯ぐきの赤みや腫れ、出血などのサインを見逃さないようにしましょう。
参照元:厚生労働省「令和4年歯科疾患実態調査」
子どもの歯肉炎の種類と原因

子どもの歯肉炎には主に4つの種類があり、それぞれ原因が異なります。ここでは、子どもが発症する歯肉炎について解説します。
不潔性歯肉炎
不潔性歯肉炎は、歯磨きが不十分な場合に起こる歯肉炎です。歯と歯ぐきの境目にプラーク(歯垢)が溜まると、歯ぐきが炎症を起こします。
また、歯磨きの力加減がわからず、歯を磨くときに力を入れすぎる子どもも少なくありません。過度な力でブラッシングをして歯ぐきを傷つけ、その傷が炎症を起こして歯肉炎になる場合もあります。
不潔性歯肉炎になった場合、歯周ポケットに溜まったプラークや歯石を取り除けば改善がみられることが多いです。
萌出性歯肉炎
萌出性歯肉炎は、乳歯や永久歯が生えてくるときに起こりやすい歯肉炎です。歯が生えてくる際に、奥歯の溝や、歯ぐきが覆い被さっている部分に汚れが溜まると、炎症が起こりやすくなります。
特に、6歳前後に生える第一大臼歯や、12歳前後に生える第二大臼歯に起こりやすいです。萌出性歯肉炎は、完全に歯が露出すると症状がおさまることがほとんどです。
思春期性歯肉炎
思春期性歯肉炎は、小学校高学年から中学生頃の思春期に多く見られる歯肉炎です。思春期は、ホルモンバランスが大きく変化し、歯ぐきに腫れや出血を起こしやすくなります。特に、女性ホルモンの影響を受けやすく、女子に多く見られる傾向があります。
栄養バランスのとれた食事や十分な睡眠など、生活習慣を整えることが大切です。
若年性歯周炎(侵襲性歯周炎)
若年性歯周炎は、思春期から若年層にかけて発症する歯周炎です。通常の歯周炎は、歯周ポケットにプラークが蓄積することで炎症を起こします。
若年性歯周炎は、プラークがそれほど多くなくても発症する場合があり、歯を支える歯槽骨が急速に破壊されるのが特徴です。歯がグラグラし始めるまでの期間が短いため、早く治療しなければなりません。
歯肉炎を予防するためにできること

子どもの歯肉炎を予防するためには、保護者の方のサポートが不可欠です。ここでは、歯肉炎を予防するためにできることを紹介します。
歯磨きを丁寧に行う
歯肉炎の原因となるプラークを取り除くためには、毎日の歯磨きが大切です。お子さまのお口のサイズに合わせた歯ブラシを選び、歯と歯ぐきの境目に歯ブラシの毛先を45度の角度で当てます。毛先が広がらない程度の力で、小刻みに動かして磨きましょう。
奥歯の溝や歯と歯の間、生えかけの歯の周りは汚れが溜まりやすいため、丁寧に磨くことが大切です。また、就寝中は唾液の分泌が少なくなるため、細菌が繁殖しやすく、歯肉炎になるリスクが高まります。就寝前は磨き残しがないよう、特に注意して磨きましょう。
12歳頃まで仕上げ磨きを行う
10〜12歳頃は、乳歯から永久歯へ生え変わり、歯並びが複雑になることが多い時期です。お子さまが自分で歯磨きができるようになってからも、小学校低学年くらいまでは保護者の方が仕上げ磨きを行ってください。
保護者の方の膝の上にお子さまの頭をのせ、仰向けに寝かせると磨きやすいです。食べかすが残っている、プラークが多く付着しているなど、磨き残しがあった箇所をお子さまに伝え、歯磨きが上手になるようにサポートしましょう。
デンタルフロスや歯間ブラシを使用する
歯と歯の間や、歯と歯・歯ぐきの間は、歯ブラシで汚れが落ちにくい部分です。乳歯が生えそろってきた2歳頃から、デンタルフロスや歯間ブラシを使って隙間の汚れを落としましょう。
プラークが固まって歯石になると、ブラッシングでは落とせなくなります。汚れが溜まってから歯石になるまでには2日ほどかかるとされているため、少なくとも1日1回はデンタルフロスや歯間ブラシを使用するとよいでしょう。
デンタルフロスを嫌がるお子さまには無理に使用せず、かわいらしいデザインや香りのついたものを使用したり、保護者が使っているのを見せたりしてみてください。
食生活を見直す
歯の健康を守るうえで、栄養バランスのとれた食事を心がけることも大切です。例えば、卵やアボカド、かぼちゃなどに多く含まれるビタミンEには、細菌への抵抗力を高める働きがあります。
ブロッコリーやいちご、キウイなどに多く含まれるビタミンCは、壊れたコラーゲンを再生する、歯ぐきの健康維持に重要な栄養素です。また、食事の際によく噛んで食べると、唾液の分泌が促され、口の中を清潔に保つ助けになります。
子どもの歯磨きへのモチベーションを高める
お子さまが歯磨きを毎日楽しく続けられるように、保護者が工夫してモチベーションを高めてあげることが大切です。例えば、好きなキャラクターの歯ブラシを選ばせたり、一緒に鏡の前で歯磨きをしたりするのも工夫のひとつです。
歯磨きができたら褒めて、カレンダーにシールを貼るのもよいでしょう。また、染め出し液を使って磨き残しを可視化すると、歯磨きへの意識を高められます。歯科医院でブラッシング指導を受けることも、子どもの歯磨き習慣を定着させる良いきっかけになるでしょう。
定期検診を受ける
ご家庭での歯磨きに加えて、定期的に歯科検診を受けることも大切です。自宅での歯磨きだけで、完全にプラークを取り除き、歯肉炎を予防することは現実的ではありません。
定期的に歯科医院で検診を受けると、歯肉炎や虫歯を初期段階で発見し、悪化する前に適切な処置を受けられます。
歯肉炎予防のための処置を受けられるのも定期検診を受けるメリットです。歯科医院のクリーニングでは、普段の歯磨きでは落とせていないプラークや歯石を除去できます。
また、お子さまの歯並びや成長段階に合わせた、より効果的なブラッシングの方法や仕上げ磨きのポイントを指導してくれます。普段の歯磨きに取り入れると、ブラッシングの質が向上し、歯や歯ぐきの健康維持につながるでしょう。
歯列矯正を行う
歯列矯正を行って整った歯並びになると、歯磨きがしやすくなり、歯肉炎や虫歯の予防につながります。歯並びがでこぼこと乱れている場合、歯が重なり合っている部分が磨きにくくなり、プラークが溜まりやすくなるためです。
歯列矯正は、歯肉炎や虫歯の予防につながるだけでなく、噛み合わせを改善して顎関節への負担を軽減したり、歯並びによっては発音しやすくなったりするメリットもあります。歯並びが気になる場合は、歯科医師に相談しましょう。
まとめ

子どもの歯ぐきの腫れや出血は、見過ごしてはいけない歯肉炎のサインです。歯肉炎には、若年性歯周炎のように進行が早く、若いうちに歯が抜け落ちる可能性のあるものもあります。
お子さまの歯ぐきの健康を守るためには、毎日丁寧な歯磨きを習慣化し、12歳頃までは仕上げ磨きを続けることが大切です。また、ビタミンCやビタミンEなど不足しやすい栄養素を意識して摂取し、食生活を整えることを心がけましょう。
定期的に歯科医院を受診すれば、お口のトラブルに早めに対処できるだけでなく、クリーニングやブラッシング指導など歯肉炎予防のためのケアも行えます。歯ぐきの腫れや出血など、気になることがあれば早めに歯科医師に相談してください。
子どもが歯肉炎かもしれないと感じた方は、横浜市神奈川区「横浜駅」きた西口より徒歩5分にある歯医者「横浜駅きた西口歯科」にお気軽にご相談ください。
当院では、予防歯科や虫歯・歯周病治療、根管治療やインプラント治療などさまざまな診療を行っています。ホームページはこちら、Web予約もお受けしておりますので、ぜひご覧ください。